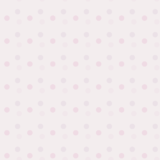この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。
バルフレアはパンネロの背を優しく撫でてやる。背中に感じる大きな温かい手がパンネロにはとても嬉しかった。強がってみたものの、もしバルフレアが迎えに来てくれなかったら、怒ったままでこのまま自分に会ってくれなかったらどうしようととても不安だったのだ。
だが、今はバルフレアの真剣な想いを知り、うれしくて、目の奥がじん、と熱くなった。そして、なんてくだらない意地を張っていたのだろうと思う。その気持ちをもっと確かめ合いたい。バルフレアは立ち上がると、パンネロの手を取って同じように立たせる。
「バルフレア、ね、連れてって。」
「病院にか?それとも、ベッドかな。」
「どうして病院なの?」
「ベッドの前にダウンタウンだ。例の薬師の所に行く。」
パンネロは身体を離し、頬をふくらませて、抗議するようにバルフレアを見上げる。
「バルフレア、私ほんとにもう大丈夫だよ!」
「念には念を入れてだ。」
「でも、フランも大丈夫だって…」
「パンネロ。」
バルフレアは体を折るようにしてパンネロの顔覗き込んだ。
「もし俺がパンネロみたいな可愛い女の子の父親だったら、絶対に薬師か医者に見せる。」
「そうかなぁ?」
「必ずそうするさ。おまけにイヴァリースで一番かわいい自分の娘が、どこの馬の骨かわからない空賊風情の恋人なんだぞ?余計にだ。」
パンネロは吹き出してしまう。そして再びバルフレアにぎゅっとしがみついた。パンネロがバルフレアに抱きついてもバルフレアの胸の辺りまでしか顔が届かない。心のなかのわだかまりがなくなったので、子ども扱いも気にならない。むしろ、その意図を知った今ではとてもうれしい。
「バルフレア、私、バルフレアのお父様とお母様が大好き。」
突然の発言にバルフレアは驚いた。そして真上からパンネロの淡い茶色の瞳を真上から見つめた。少し眉を寄せ、困惑した表情になる。
「私、思うの。バルフレアが私に優しくしてくれたのは、お父様とお母様がバルフレアに優しかったからだって。」
「だが俺の親父はお前の…」
「私、そんな風に思ったことなんか、一度もないよ。」
きっぱりと言い切るパンネロにバルフレア返事すらできない。
「バルフレアがくれるプレゼント、最初は値段に驚いたの。でも、ドレスも靴も宝石も、どれも私にとっても似合うのばかり。バルフレアはちゃんと私を見て私に似合う、私が喜ぶものを選んでくれていたんだね。」
パンネロは身体を離すと、バルフレアの手を引いて、自分から部屋のドアへと向かう。
「きっとバルフレアのお父様とお母様も同じことしたんだって思うの。だから会った事は無いけれど、私、あなたのお母様が大好き。」
ドアを開けパンネロは先に通路に出て、驚いた表情で自分を見つめるバルフレアを穏やかに見つめ返した。
「私が家族を亡くしたのは、あなたのお父様のせいかもしれない。でもね、大灯台で戦ったとき、最後にお父様はあなたのお父様に戻ったと思う。私、それで、もういいやって思ったの。」
自分の父親のせいで大きな戦乱が起こった。結果、パンネロの家族はその犠牲となった。バルフレアの中にそれがずっと心の中に残っていた。そのことに気付いていてくれたのかと、優しいパンネロの言葉が嬉しい。
「私、バルフレアがご両親からもらった優しさを、私にも分けてくれているような気になる。」
「そうか。」
小さな頭の上に手を置き、くしゃっと髪を撫でる。
「ちゃんと診てもらって、何もなかったら飯でも食うか。」
「私、お腹ペコペコ。ずっと食べてなかったの。食べたくなかったの。」
「俺もだ。喧嘩の代償は高くついたな。」
バルフレアは部屋の鍵を閉じながら肩を竦めて見せた。パンネロはすぐにバルフレアの腕に自分の腕を絡めた。
「ね、もう本当に怒って……ない……?」
「怒ってないさ。」
「本当に?」
「ああ。なんなら証明してみようか?」
「どうやって?」
「今から飲む苦い薬のあとでも、ちゃんとそのかわいい唇にキスしよう。」
苦い薬と聞いて、下唇と尖らせ、パンネロはバルフレアを睨みつける。バルフレアは笑いながらパンネロの肩を抱き、ダウンタウンの方へと歩き出した。
*************
フランお墨付きの薬師屋に足を運び、薬師に簡単な問診と、魔法をつかった心霊的な診察を受けた。大丈夫だと告げられ、バルフレアは肩をなでおろし、ついでにこの騒動の原因となった貰いそびれた傷薬も受け取った。
代金を支払うバルフレアを待つ間、パンネロは周りをぐるりと見回す。パンネロに大人になる薬をくれた老婆の店はもうなくなっていた。
「どうした?」
バルフレアが優しく肩を抱いてくる。あの占い師のことはバルフレアに言わないでおこうとパンネロは心に決めた。
『そうやって年の離れた恋人を持ちたがる男っていうのは、女をお人形みたいに思っているのさ。』
なんて言われたこと、そしてそんな言葉にパンネロがのせられたと、もしバルフレアが知ったら大変だ。パンネロは知る由もないのだが、その占い師と一味はバルフレアによって、とっくにどこかへ追い出されていたあとなのだ。
「……ううん、なんでもない。」
パンネロは市街地に出る階段の方へと先に立って歩き出す。ぴったりとバルフレアの腕に身体をくっつけるようにして歩き、バルフレアは時おり身体を屈め、パンネロの前髪に唇を落とす。仲直りのあと、こうやって背の違いを埋めるように、バルフレアがいつも自分を気遣ってくれていることを、パンネロは思い出した。
(私…大切にされているんだ……)
そう確信するとともに、どうしてこんなに不安になってしまったのか、パンネロは自分でもよくわからくなってしまったのだった。
***********
部屋にもどると、すぐに抱き上げられてベッドに連れていかれた。バルフレアはベッドに連れて行く時は必ず抱いて連れて行ってくれる。パンネロはその瞬間が大好きだ。たくましい腕に自分の体重なんてないかのように軽々と抱き上げられるのは、ほんとうに心地よい。そして連れていかれたベッドの上で、寂しかった日々と心細さを埋める位めちゃくちゃに愛して欲しかった。
すぐに横たえられるのかと思ったが、バルフレアはパンネロをベッドの端に座らせると、まずブーツを脱がせ始めた。膝の横のバックルを外し、丁寧にそれを引き抜いてベッドの下に置く。そして何も異常がないかと注意深く見守り、かわいらしい膝小僧にチュッと音を立ててキスをした。ついでに太もものバックルも外しておく。
手首に巻かれたボリュームのある革製のバングルを外し、それから胸元の留め具を外し、背中の羽根飾りを外す。肌が露わになると、バルフレアは厳しく目を開かせ、納得すると次へと移り、パンネロの装身具を外していく。
ほっそりとした顎の下のファスナーを下げ、複雑な仕組みのスーツを脱がせ終える、と今度は中に着ていたスタンドネックのブラウスだ。ボタンを外して脱がせ、下着だけの姿にしてしまう。恥ずかしそうにもじもじと首をすくめていたパンネロだが、バルフレアの真剣な眼差しに引き込まれていって、黙ってその作業を見守った。
ぴったりとした服にラインが出ないための、なんの飾りもついていない、だがせめて色だけはかわいいものをと選んだ淡いブルーの下着姿になると、バルフレアはもう一度パンネロの身体を上から下まで検分し、満足気に頷いた。次は髪だ。
羽飾りを丁寧に外し、髪の間に指をいれ、ゆるく編まれた髪をほどいた。柔らかいハチミツ色の髪を指に絡め、目を細めその感触を味わう表情に、パンネロの胸がときめく。
「バルフレア、私、心臓が破裂しそう……」
か細い声が鼓膜に心地よい。バルフレアはゆっくりとパンネロの身体をベッドに倒し、その上に覆いかぶさる。
「バルフレア、お洋服。」
「おっと。」
「あ、待って。」
起き上がろうとするバルフレアに、パンネロがきゅっとしがみついた。
「ちょっとだけ、ぎゅってさせて。」
「パンネロ……」
「私を……安心させて……」
長い腕が包みこむようにパンネロを抱きしめた。服越しではあるが、バルフレアの体温を感じた。重なりあった心臓がとくとくと優しく、どちらが自分のものなのか分からなくなる。パンネロは満足したのか、ほう、と大きく息を吐いた。バルフレアの瞳がパンネロの瞳を覗きこむ。青と黄色が交じり合って作る、不思議な緑の虹彩に、パンネロの胸がとくんと高鳴り、慌てて目を反らした。
「パンネロ?」
咎めるような声に、意を決して瞳を見つめ返した。頭の中で数を数え、なんとかこらえようとするが、ものの5秒でパンネロは照れて、バルフレアの胸に顔を埋めてしまう。
「俺はまだ服も脱いでないんだぞ?」
「だって……もう、知っているくせに……」
「パンネロの口ぐせだ。“だって”ばかりだ。」
「……そうかな?」
「ああ。普段やイイ子なのに、ベッドの中でだけ、な。」
だって、それはあなたのせい、と言いかけてパンネロは口をつぐみ、きゅっとシャツの袖を掴んだ。
(だって、ばかり言ってたら子供っぽいよね…)
そう考えなおし、腕を伸ばし、バルフレアのベストのカラーを外し、背中の留め具を外した。
「いい。あとは自分でする。」
パンネロが頷いてみせると、バルフレアは膝で立ち、着ているものを全て脱ぎ捨てると、パンネロを抱いてシーツの中に潜り込んだ。頬や胸にふれる固くしなやかな身体と体温はパンネロを安心させ、穏やかな気持ちにさせる。
「いつまでそうしているんだ?俺はまだ、一度もキスをしてもらってないんだが?」
そんな意地悪を言いながらも、バルフレアの手は優しくパンネロの頭を撫でる。
「だって……」
「また“だって”だ。」
「もう……!」
ぷぅ、と頬をふくらませ、胸の中からバルフレアをにらむ。が、見つめ返された瞳がひどく艶めかしく、パンネロは息が止まりそうになる。そうして、またこの不思議な色と力を持つ瞳に捕らえられてしまったと思う。
(いつもは…すごく優しいのに……こんな時は……)
どんどん身体が熱くなっていって、心臓の鼓動はパンネロの薄い胸を破ってしまいそうだ。
「どうした?」
誘うようなささやきに、パンネロは引き寄せられるようにバルフレアの口唇に、おずおずと自分の口唇を重ねた。
「……ん、……」
やわらかく包み込むような口唇と、伝わってくる体温に陶然となり、パンネロはうっとりとした声をもらした。その声が引き金になったのか、バルフレアの口づけは、強く、深くなる。息苦しさに口唇を薄く開くと、バルフレアはその瞬間を逃さず、舌を差し入れた。
「……ふっ……!」
ねっとりとした熱い舌に、パンネロの小さな舌はあっという間に捕らえられた。パンネロの肩が跳ね、そのまま固まって動けなくなる。バルフレアの舌はパンネロの口内を思うさま暴れ、舌を吸い上げた。
「……ぅ、……んっ、……」
もう腰のあたりが甘くうずいていた。まだ口唇を合わせただけなのに、身体は火照り、腰の奥の方にじんわりとした愉悦がもう溜まり始めているのに、パンネロはいたたまれなくなって身体を離そうとする。すると、バルフレアよりも熱をこめ、パンネロの舌の表面を、ぞわり、と舐め上げた。
「……ぁ、……あ、……」
鼻にかかった甘さのある声が漏れたのをいいことに、バルフレアは何度もそれを繰り返してくる。パンネロはたちまち力が抜けてしまう。バルフレアはそれに気づくと、今度は舌を絡めて吸い上げる。
「はっ……、あっ……」
背中をぞくぞくした感触が這い上がる。たまらず、パンネロはバルフレアに強くしがみついた。背中を駆け上がる感触は止むことがない。バルフレアのキスは情熱的だった。ほんの少し舌を動かすだけで、パンネロは肩を跳ねさせ、その感触にどんどん考える力を失っていく。
銀の糸を引いて口唇が離れること、パンネロはぐったりとしており、どこまでもシーツに身体が沈んでいくような気がした。
「あ……バルフレア……」
頼りなげな声で呼ぶと、大丈夫だという答えのかわりに強く抱きしめられた。