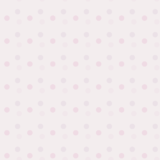この記事を読むのに必要な時間は約 13 分です。
「パンネロ……、たまらないな。」
キスだけで達してしまうのではないかと思うほど感じやすくなっているパンネロは、壊れやすそうに繊細で、そして可憐だ。そんな恋人にバルフレアも我を忘れそうになる。
「バルフレア……」
視線が絡みあう。パンネロはもう完全にバルフレアの与える官能の虜だ。見つめられる瞳を、もう反らすことができない。ただ、次に与えられるキスを待つだけだ。うっすらと口を開く。と、すぐまたくちびるが重ねられた。息ができないほど激しく貪られ、パンネロはぽろぽろと涙をこぼす。
パンネロが抵抗できないのをいいことに、その最中にバルフレアはパンネロの下着の背中の留め金を片手で器用に外してしまう。胸を包んでいたそれがふっと緩んだかと思うと、もう肩から紐が引きぬかれ、ほんの少し身体が離れた合間にもう抜き取られていた。バルフレアは左手でパンネロの腰を抱き、右手で下履きを掴んで引き下ろした。
「んんっ……!」
いや、と声を上げたいが口唇はまだ塞がれたままだ。陰部を覆っていたそれが剥がされたとき、もうたっぷりと溢れ、流れていた蜜が、にちゃ、と音を立てたような気がしてパンネロは恥ずかしくてたまらない。だが、しっかりと抱きとめられ、口内を犯された状態ではなんの抵抗もできない。バルフレアはもじもじと腿をこすりあわせるパンネロの動きに合わせ、あっという間にそれを足から抜き取ってしまう。
「パンネロ……」
バルフレアが耳元でささやき、パンネロの手を取り自身の身体の中央にあてがう。そこはもう猛りきっていて、とろとろとこぼれた先走りの液のせいで、ぬらぬらと濡れていた。
「俺だって、もう、こんなだ。」
やっぱりバルフレアにはバレていたのだと知って、でも、バルフレアも自身を破裂させそうなほど自分を欲しているのだとわかると、パンネロは恥じらいと羞恥心の両方を、あっという間に手放した。熱いその塊を、小さな手で優しく握りしめた。すると、バルフレアが小さく息を吐いたのがわかった。
「バルフレアも……ね、触って……」
バルフレアはぴったりとくっついた胸と胸の間に手を滑り込ませてきた。
「んっ…!」
小ぶりな、だがしっかりとした弾力をもつ胸を大きな手で完全に覆ってしまうと、指と手のひら全体を使って揉みしだく。自然と顔と顔が近づき、口唇が合わさった。パンネロはすぐに口唇を開き、バルフレアのものを招き入れた。舌そのものが生きた小さな蛇のように、意志を持って絡み合うようだ。
手のひらに感じるバルフレアの欲望と、胸からこみ上げ、瞬く間に全身を支配した愉悦、嵐のような口づけに、パンネロは溺れるものが必死で水面に顔を出そうとするかのように、絡められる舌を追い、手の中のモノを扱き上げた。
ふっとバルフレアの身体と口唇が離れた。夢中でしがみついていたぬくもりと、手の中の熱を見失い、うっすらと目をあけた。すると、バルフレアが、早くなぶって欲しいと言わんばかりに赤く尖った乳首を口にふくむところで、パンネロは慌てて目を閉じた。
「あ、んっ……ん……!」
華奢な身体が大きくびくりと震えた。バルフレアはそこを吸い上げたり、舌を使ってざらり、と舐め上げたりと様々な手管で愛撫する。
「あぁ……」
バルフレアの頭を抱きしめ、パンネロはのどを反らせた。舌で舐められるとむずがゆいような、そして歯を立てられると、ピリッとした刺激がそこから沸き上がる。緩急をつけられた愛撫にパンネロは弱い。ぎゅっとバルフレアの頭を抱きしめたまま、下半身はじっとしていられずに、腿をもぞもぞとこすりあわせたかと思うと、足をぴん、とつっぱらせた。
「ん……んっ……」
反対側を、指で転がされる。
「あっ……!」
パンネロは身体をこわばらせ、バルフレアの髪をくしゃくしゃにかきまわす。両方の胸から絶え間なく与えられる快感に、息は弾み、淡い色をした可憐な突起はどんどんと赤く熟れ、尖っていく。いじられればいじられるほど、乳首はどんどん敏感になる。ほんの少し舌が掠っただけの刺激でも、びくんと身体が跳ねてしまう。
「ぁ……ん!や、バルフレア……っ」
バルフレアがそこを舌で愛撫し、その際にもれる、くちゅ、という音が耳から下肢に伝わり、暖かく湿った秘裂から愛液が溢れて止まらない。
「だ、め、バルフレア…そこ……ばっかり……、あん!」
今日のバルフレアの胸への愛撫は執拗だった。そこから沸き上がる快楽に頭は沸騰しそうなのに、バルフレアいつまでたっても次の、もっと気持ちいいアレをくれないのだ。秘裂の奥から蜜はとめどなく流れ、そこへの愛撫を待ってうねうねとうごめいている。先端の花芯も、早く触れて欲しいと花びらのような包皮から顔をのぞかせ、ズキズキとうずいているのに。
もどかしさに、頭がおかしくなりそうだ。無意識にむっちりとした太ももを擦り合わせ、もじもじと腰を跳ねさせる。
「あっ!バルフレア、わたし、おかしく……なっちゃう!やっ!もう!」
パンネロは狂ったように頭を振り、足をつっぱらせては、擦り過ぎた太ももが赤く染まる。
「や――ぁっ……ああああっ!」
突然、パンネロは悲鳴を上げて達した。バルフレアはにやり、と笑ってびくびくと絶頂の余韻に身体を震わせるパンネロを見下ろした。
「胸だけで、イっちまったのか、パンネロは?」
「あ…っ!あ…っ、ちが……きゃあ!」
パンネロが悲鳴を上げたのは、達したばかりのそこをバルフレアがぬるり、と指の腹で撫でたからだ。
「違わないだろ?」
そこは未だに絶頂の余韻でぴくぴくと跳ね、その度にパンネロは身体を跳ねさせている。
「やっ!さわ…っちゃ、……ダメ!違う……の!足…をね、もじもじさせていたら……」
「なるほど……な。」
どうやら足を擦り合わせたそれがクリトリスへの刺激となり、胸の愛撫と合わせて達してしまったようだ。
「今までで、最短じゃないか?パンネロ。」
耳元でそうささやくと、パンネロは顔を伏せ、恥じらいにきゅっと目を閉じた。その様があまりにもかわいらしく、バルフレアは指に触れ、まだ痙攣を繰り返す、小さな小さな肉芽をキュッと摘んだ。
「〜〜〜〜〜〜〜っ!」
強すぎる快感に、パンネロは歯を食いしばり、バルフレアにしがみついた。感じすぎたパンネロが、指を食い込ませんばかりにしがみつかれるのがうれしい。バルフレアは上機嫌で、達したばかりでひどく敏感になっているそこを、もう一度つまみ上げた。
「あぁ――――――――っ!」
ほんのひと撫ででパンネロはあっけなく、だが、激しく達してしまい、身体を弓なりに反らせ、悲鳴を上げた。
「バル…フレア……、いや……ぁ……っ」
絶頂の余韻に身体を震わせ、強すぎる快感にしゃくりを上げて泣きだした。体内を暴れまわる快感を抑えようとするパンネロに呼ばれる自分の名前は、どうしてこんなに甘美に耳をくすぐるのだろう。
「パンネロ。」
涙で赤くなった瞳で、パンネロはバルフレアを見つめる。
「心配かけたおしおきだ。ここを……」
そう言って、バルフレアは二度の絶頂でくったりと力を失った陰核を、再びぬるり、と撫でた。
「やぁっ!あっ、……あっ……!」
細い腰を跳ねさせ暴れるパンネロに覆いかぶさり、その顔を真上から覗き込み、なおも言葉で追い詰める。
「そうだな、気持ちよすぎて、気を失うまでいじってやる。」
パンネロはその言葉に、大きく首を左右にふる。だが、逃げようにも大きな身体で抑えこまれ、サディスティックなのに甘い言葉に自由を奪われ、許して、とうったえかけるように見つめ返すしかできない。
もう、今にでも気を失ってしまいたい、そう思って瞳に涙をためているパンネロに、バルフレアは優しく微笑みかける。鼻の頭にちゅっ、と音を立ててキスをしてやる。それは、パンネロのオイタをいさめる時のキスだ。パンネロはバルフレアが冗談で言っているのではないことを理解した。背筋を、戦慄が駆け上がった。
バルフレアはゆっくりと、さんざんねぶられ、未だ痛いほどに尖っている乳首にそっと歯を立てた。
「やっ……ん! 歯、ダメ……!あっ!」
とっぷりと愛液に浸っている赤い小さな実を、包皮を剥いて露出させる、中指でゆるゆると撫でる。
「あぁっ!あっ!……やっだ…ぁ……!」
身体の下で暴れ、バルフレアの身体を押し返そうとするパンネロの両手首を掴み、シーツに押し付けた。
「やぁっ!いやぁ!あっ!……バルフレア…!やだやだ!」
溢れる蜜はバルフレアの指をぐっしょりと濡らす。何度も達したそこは、絶頂のような激しい快感をパンネロに絶え間なく与え続ける。パンネロは泣き叫び、足をバタつかせて暴れた。
「バルフレア……もっ…だ、め……っ!」
はっはっと短い息を吐き、身体を強ばらせては弛緩を繰り返す。もうすぐ弾ける、そのタイミングでバルフレアは、ふっと手を離した。何が起こったかわからないパンネロは呆然とバルフレアを見つめる。
「バルフレア……?」
中途半端な状態で愛撫を止められて、パンネロは困ったように眉を寄せた。手首は押さえつけられたままだ。自分ではどうすることもできない。
「……ひどい。」
ぽつん、とつぶやいた声がまたかわいらしかった。官能の最中にいるのに、頬をふくらませ、口唇を尖らせて。
「バルフレア、ヒドいよ……おしおき、なんて……私……」
哀願する様がまたそそるのだ。もっといじめたいという欲望に目がくらみそうになる。
「そうだな……」
パンネロを安心させるために、手首を解放してやる。パンネロはホッとした表情を浮かべた。
「ごめんな。おしおきなんて、ガキの言いがかりだ。」
バルフレアは優しくパンネロの頬を撫でた。わかってくれたのだとパンネロも、バルフレアの手に自分の手を重ねた。本当は抱きつきたかったのだが、身体中の力が抜けて、それが精一杯なのだ。
「お前が嫌がると、それがかわいくて、な。」
パンネロは、いいの、言う代わりに頭を左右に振った。
「だから、はっきり言わせてもらうぜ。お前が、感じて、悲鳴をあげている所がもっと見たい、ってな。」
驚いたパンネロが逃げ出そうとする前に、バルフレアはパンネロの腰を抱いて、背中から抱きすくめてしまう。
「やん!バルフレア、ズルい!」
「ズルくって結構だ。」
そして胸をぎゅっとつかみ、淡い色の茂みの奥へと手を伸ばした。
「あっ!やだ!」
達する寸前で止められた愛撫を不意に再開され、パンネロの身体からあっけなく力が抜けた。だがバルフレアの意地悪に、意地になっているのか、声を出すまいと歯を食いしばる。
「パンネロ。」
耳元で名前を呼ばれた。いつもならそれだけで身体の力が抜けるのだが、パンネロはすっかり頑なになってしまい、バルフレアに頭がぶつかってしまうのではないか、という勢いで頭を左右に振る。バルフレアは、やれやれ、と首にかかる髪をかきわけ、あらわれた白いうなじに口唇を押し付けた。
「バルフレア…、ひどい……」
「ずいぶんな言い様だな。」
「だって、それが聞きたいんでしょ?ひどい、とか、イヤ、とか。仲直りの………なのに。」
「仲直りのなんだって?」
「もう!」
言葉尻をとらえてからかうバルフレアにパンネロは、肩越しにキッとにらむ。だが、そんな表情すらも、バルフレアにしてみるとかわいくて仕方がないのだが。
「そうだな、仲直りのセックスだ。」
あからさまな言い方に、パンネロが赤い顔を更に赤くする。
「だから、俺もはしゃぎ過ぎた。悪かった。」
バルフレアはパンネロを正面からしっかりと抱きしめた。バルフレアが部屋にやって来たとき、キスや抱きしめることでごまかさないで、と叫んだが、今がまさにそれだ。だが、言葉よりも強く抱きしめられることで、より気持ちが伝わることもあるのだ。
「もう、意地悪しない?」
「ああ、しない。」
「優しくしてほしいの。」
「約束する。」
パンネロの身体から力が抜け、愛らしい笑顔を見せた。それはバルフレアの決意を惑わせるほど蠱惑的だった。噛み締めたせいで腫れてしまった口唇に優しくキスをし、自分の気持ちを鎮めてから、パンネロを横たえた。