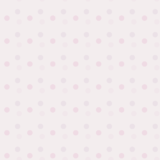この記事を読むのに必要な時間は約 15 分です。
部屋に入った途端飛んできたクッションを、バルフレアは首を軽く傾げて避けた。
扉を開けたその正面に大きな窓があり、その横のソファにパンネロは座っていた。そこにあるジャガード織りで細かい花がらが織り込まれたクッションを、パンネロは手に取ってはバルフレアに投げつける。
「知らない!バルフレア……!私、怒ってるの!」
バルフレアはひと言も喋らない。ただ、真剣な顔で、パンネロに歩みよる。時折飛んでくるクッションは避けるか、手ではたき落とした。
「もう!来ないで!き、キライ!バルフレア、キライなんだからっ!」
眉一つ動かさず、眉間をぎゅっと寄せ、口を一文字に結んでるバルフレアの表情にパンネロは怯えた。が、パンネロはすごく傷付いたのだ。キレイと言ってもらいたかっただけなのだ。なのに、あんなに怒られて、
(怖かった……し……)
そして、怒られたって負けるものか!と意地になる。乙女心を踏みにじられたのだ。頑張って爪を染め、そこに良い香りがする香料を一滴垂らし、大理石のような紋様を小さな爪の上に作ったことがあった。爪からほのかに良い香りがして、バルフレアはそれを褒めてくれた。慣れないこてを駆使して作った、髪の毛先だけをゆるく巻いた髪もとても気に入ってくれた。きれいな青い色の粉を、まぶたではなく、目の下に薄く塗って、下まつ毛にも軽くまぶした時だって、すぐに気が付いた。パンネロにしては思い切った、赤みがかかったピンクの口紅を塗り、唇のふっくらした所に人差し指でハチミツをちょん、とのせて、ぷるん、とした艶を出したときだって、
(“食っちまいたいほどかわいい”って、言ってくれたのに……っ!)
無表情でひと言も話さないバルフレアに何か言わせたくて、パンネロは目の前のバルフレアの顔めがけて思い切りクッションを投げた。それは、ばふっ、と空気が抜けるような音とともにバルフレアの顔を直撃した。どうせ避けるだろうと高をくくっていたパンネロは驚いて、クッションを投げたままの姿勢で固まってしまう。そうして理解する。いつものバルフレアではない。パンネロの怒りなんて、取るに足らない、子どものワガママなのだと思い知らされてしまう。
バルフレアは足元に落ちた最後のクッションを、目障りだと靴の先で転がし、乱れた髪をひと撫でした。もうクッションはない。バルフレアの足を、いや、クッションなどバルフレアの進撃を止めるのに、なんの役にも立っていなかったのだが。バルフレアはじろり、とパンネロを見下ろす。視線に圧迫され、パンネロは後ずさるが、ソファの後ろに逃げ場などない。唇がこわばり、手が震えた。バルフレアの手が自分に向かって伸びてくる。殴られる、そう思ってぎゅっと目を閉じた。と、同時に抱きすくめらた。
「バル…フレア……?」
バルフレアはパンネロの全てを覆うように、小さな身体を自分の身体で閉じ込めるようにして、パンネロを抱きしめていた。叱られる、そう思い込んでいたパンネロは驚いて目を見開いた。顔をバルフレアの胸の辺りに引き寄せられるようにして抱かれているので、パンネロはバルフレアの表情をうかがうことはできない。だが、慈しむように髪を撫でられて、自分がどれだけ恋人に心配をかけたか、そして恋人がどれほど心を痛めていたか、抱きしめた身体が少し痩せていたことから、ようやく理解した。
抱きしめられて、猛烈な勢いでパンネロは自分の行いを悔やみ始めた。
(でも……!)
まるで、殻を破くことができないひな鳥のようにパンネロは暴れ始めた。
分かったのだ。「かわいいよ。」と言われることはパンネロにとって、とてもとても大切なことなのだ。それは「小さい子どものようにかわいい」とか「愛らしい生き物のようにかわいい」ではない。「きれい」と同意義で、かわいい、言ってもらいたかったのだ。どれほど頑張っても、自分のささやかなドレスアップは洒落者のバルフレアにふさわしいのだろうかと、いつだって不安だった。その不安をバルフレアは、
(わかってない!)
肩の骨が砕けるのではないかと思うほど、しっかりと自分を抱きしめる腕をなんとか解こうとパンネロはもがいた。だが、万力のようにガッチリと自分を締め付ける腕をどうしても振り解くことができない。
「ご、ごまかされないんだから…!そうやって、ぎゅってしたり、キスしたり!いつも…!」
違う、とパンネロは心の中で自分の発言を否定する。確かに何かをごまかそうとしてパンネロを突然抱きしめたり、唇を塞がれるいことはあった。だが、それは他愛のないお遊びの時だけだ。真剣なときは、そんなふうにふざけたりしないのを、パンネロは誰よりもよく知っていた。
でも、止められないのだ。こんなにも愛されて、幸せなのに、どうして苦しいの!そう叫びたい。
「き…らい……!バルフレアなんか……きらい、なんだから!」
「きらい。」と言葉にすると、まるで世界を滅ぼす呪文を唱えたような気がした。だが、不安な気持ちはパンネロの言葉を乗っとり、心にもない言葉を吐き出させる。
(違う……やめて……きらいなんかじゃないのに……)
大人になれば。パンネロは思った。好きになればなるほど不安になる気持ちも、もっと背が伸びて髪は豊かに、胸は膨らんで、長いまつげを伏せた影がつくる憂いを帯びた眼差しを手に入れれば、全てが解決するのだ。
(だから……私……!)
「私!大人になりたいの!早く……今すぐにでも!!」
叫んで、パンネロは息を詰めてバルフレアの反応を待った。もっと怒るだろうか?ひょっとして、言い過ぎたのではないだろうか?嫌われてしまったのでは、という恐怖にパンネロが身体を固くしたそのとき、バルフレアがポツリとつぶやいた。
「おまえが……」
ようやく口を開いたバルフレアに、パンネロは次の言葉を緊張して待った。
「無事で……良かった……」
絞りだすような声に、涙が堰を切ったように溢れ、流れた。
「バルフレア……」
そうして、パンネロは初めて気が付いた。自分を抱きしめるバルフレアの腕が震えていることに。
「ごめん……ごめんなさい……」
抱きしめるバルフレアにほだされるものかと意固地になっていたことを激しく悔やんだ。
「バルフレア、ごめんね。心配かけて、ごめんね……」
「いい。何も言うな。」
とうとうしゃくりを上げて泣きだしたパンネロの髪を、バルフレアは優しく撫でてやる。
「だって…だって…」
パンネロは声を詰まらせながら、それでも、申し訳ない気持ちと、意地を張っていた緊張感が一挙に緩んだせいで、感情が爆発してしまう。
「怖かったの。バルフレア、とてもとても怖かったの!あんなに怒るって思わなかったんだもん!でもね、嫌いって言ったのは嘘なの!そんなこと思ってないよ。だから……」
「お前が俺が嫌いになるなんてないって、ちゃんとわかってるさ。」
「大人になったら……大丈夫だと思ったの。もう、不安なんてなくなるって。好きなのに苦しくなったり、好きなのに不安になったり!そんなこと……!」
「パンネロ。」
バルフレアは低い、だがしっかりとした声でパンネロの名前を呼んだ。
「大丈夫だ。なにも、心配しなくていい。」
泣きじゃくって、呼吸すらまともにできなかったパンネロだが、その言葉が波立つ心を徐々に鎮めていってくれるようで。
パンネロの泣き声が控えめになったところで、バルフレア身体を離し、パンネロを抱いたままソファに座り直した。そのまま小さな頭を抱き、優しく髪を撫でる。
「どうして……大丈夫なの……?こんなにも、こんなにも…悲しくなって、子ども扱いはイヤなのに、本当にちっちゃな子どもみたいに泣いちゃって……」
パンネロはまだ涙をポロポロとこぼしている。バルフレアは、パンネロのまぶたにそっと口づけた。
「お前が何を不安に思っているか、俺にはわからんさ。だが、な、パンネロ。どうして不安になるかはわかる。」
「“俺のことが好きだから”っていうのはダメだよ?」
パンネロはまだ半信半疑のようだ。そんな憎まれ口をいう。そんなパンネロに、バルフレアはもちろんだ、と頷いてみせる。
「それは、な、パンネロ。お前がかわいい女の子だからさ。」
意外な返答に、パンネロはびっくりして声が出ない。目をぱちぱちと瞬かせていだが、たちまち眉を寄せ、プンプンと怒り出す。
「そんなの、答えにならないよ!」
「そうでもないさ。」
バルフレアは肩をすくめ、にやりと笑ってみせる。パンネロが泣き止み、ようやく表情が戻り、瞳に光が戻ってきたからだ。そうして、パンネロの鼻を、きゅっと軽くつまんでみせる。
「パンネロみたいに可愛い女の子はな、夕陽を見ただけで涙ぐんだり、デートに出かけるときに雨が降ってるってだけで泣き出したりするもんさ。」
自分の悩みはそんな軽いものではない!そう抗議しようとしてパンネロはふと考える。バルフレアは何度も自分のことを好きだと伝えてくれた。デートや贈り物だけではない。パンネロの悲しみに共感し、寄り添ってくれてきたではないか。
そこまでして自分を大切にしてくれるバルフレアに、どうして不安になる必要があるのだろか?
「い、今はそうかもしれないけど、いつかはって、思っちゃうの!」
「前に、きれいに染めた爪を見せてくれたな。」
覚えていてくれたんだ!と、こんな時でもパンネロはうれしくなってしまう。でも、今は乙女心を軽んじたことを分からせたい!と思っているので顔に出さないようにこらえる。
「せっかくきれいに染めても、出かける時に爪が折れちまうかもしれないだろ?」
「…そうだけど……」
「俺が贈った服も、にわか雨でしみになったら、それは誰のせいだ?」
「…えっと……」
パンネロは賢い子だ。もう、バルフレアが言おうとすることは理解した。
「そうだけど……」
パンネロの不安は2人の関係の未来が、もっと具体的に言うと、自分よりも“大人な女性”が現れ、バルフレアはその女性を好きになって、パンネロの元から去ってしまったら、ということだ。バルフレアの喩えは“これだけ愛し合っているのだから、そんな心配はするだけ無駄だ”という楽観主義的な考えで。パンネロは、ぷぅ、と頬をふくらませる。
「バルフレア、ずるい。」
「空賊には最高の褒め言葉だな。」
「そうなんだけど…!私、それが気になっちゃうんだもの。気にしてもしかたないって言われても、気になって不安になるの!それを“かわいい”とか、“女の子”だからって言われても、納得できないよ……」
「パンネロ。」
バルフレアは目を細めてパンネロを見つめていた。パンネロは急に自分の言動が気恥ずかしくなり、慌てて目を反らせた。バルフレアはパンネロの細いあごを指でそっと捕らえ、上を向かせると、
「心配しなくても、お前は大人になる。」
「いつ?」
まるで明日?とでも言い出しそうに身を乗り出すパンネロがかわいらしい。
「さぁな。明日かもしれないぜ?」
「嘘。」
「そうだな。だが、パンネロ、いいことを教えてやる。」
パンネロの柔らかい頬を手の甲で撫で、指先で、ふに、と柔らかいそこを突いてみる。パンネロは騙されてなるものか、と、強情に口を結んでいるが。
「大人になれば、お前の不安なんて消し飛んでるさ。それが明日か、1年先か、俺にもわからないが、な。」
バルフレアは指先を滑らせ、パンネロの唇をたどり、鼻をたどり、額に触れる。まるで、“今”のパンネロを愛でているようだ。
「パンネロ、お前はそれはきれいな女になるだろう。男たちが震いつきたくなるような、な。」
じゃあ、どうして大人になった自分を、キスどころかロクに見ようとしなかったのか。パンネロにはそれが不満で、唇を尖らせる。
「だが、忘れるな。その頃俺は、腹が出た親父になってるかもしれないぜ?」
訝しげな表情が、くるんと一回転し、鳩が豆鉄砲を食ったような顔になる。目を丸くして驚いてバルフレアの胸を、小さな拳でぽかぽかと叩く。
「やだ…!そんなの…!」
バルフレアは優しくパンネロの両手首を捕らえ、その顔を正面から真っ直ぐに見つめる。途端にパンネロはキュッと瞳を閉じて、首をすくませてしまう。
「パンネロ、小さい頃のお前はかわいらしい女の子だったんだろう。そして、未来のお前は、イヴァリースで一番の美姫になるだろう。」
「本当?」
「本当だ。」
バルフレアはパンネロの手首を掴む手に、ぐっと力をこめた。
「だがな。」
それにつられて、顔を伏せていたパンネロが顔を上げた。
「俺が命をかけて愛し、何があっても守りたいと思うのは、今のお前だけだ。」
バルフレアが何を言っているのかわからず、パンネロは口を半分だけ開き、まるで自分の知らない言葉で話しかけられたような顔でバルフレアを見つめ返した。
「俺はな、パンネロ。こんなにも愛おしくて何にかえても守りたいと思える、そんな女に会えるなんて、あるはずがないと思っていた。ずっと、ずっとだ。そんな夢みたいな話、俺にはありっこないってな。」
パンネロは口を閉じるのも忘れ、バルフレアの顔を見つめ返す。
「誰も、俺を救えないと思っていた。俺自身にもだ。俺は死ぬまで、目をそむけたい物を隠すために、小さなスコップで砂をかけ続けて生きていくのだと思っていた。だが、お前が現れた。」
そこでバルフレアは言葉を切った。パンネロはそれでもしばらくバルフレアの顔を見つめていたが、突然、まるで頭から蒸気を出しそうなほど、顔を真赤にしてうつむいてしまった。
「は、は、離して…バルフレア、私……顔、真っ赤で……」
やっとの思いでそれだけを口にする。バルフレアが手を離し、そっとパンネロを引き寄せる。握られていた手首がジンジンする。それはバルフレアの真剣さの現れだ。パンネロは火照った頬をバルフレアの胸に押し付けた。
「お前は、川をぐんぐんさかのぼる若い鮎だ。かわいらしくて、命に溢れてる。薬だか魔法だか知らねぇが、そんなもんに頼ったりしないでくれ。」
きっと顔はまだ赤いままだろう。泣きはらして目だってはれているに違いない。だが、パンネロはバルフレアの瞳を見上げた。よくみると、目の下が黒い。あまり眠っていないのだろう。
「もう、しない。」
「約束するか?」
「約束する。」
パンネロは小指を差し出した。バルフレアはそれに自分の指を絡めた。
「でも、私、きっとまた不安になって、臆病になる。バルフレアを困らせる。」
「それでいい。お前は、お前のままでいてくれ。俺のことを、俺に会うことで頭がいっぱいで鏡に向かう、お前が好きだ。」
パンネロは腕を伸ばし、バルフレアの首に巻き付け、そのままきゅっとしがみついた。