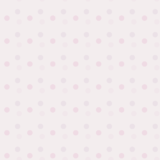この記事を読むのに必要な時間は約 17 分です。
バルフレアがどこかの遺跡から盗んできたというご自慢のお宝を見せてもらっている時、その事故は起きた。
宝石商よりも学者が好みそうな古い短剣だった。派手な宝石もついていない、工房でいちどきに作られた物だろう。だが、鉄ではなく銅で出来ているそれを見て、現在発見されている最古の物と同じくらい古いこと、錆びてはいるが、血の跡があることから実戦で使われた物らしく、バルフレアはその発見に少々興奮しているようだった。短剣をみがき、柄の細工が最古の物と同じだとパンネロに見せようと持っていた手首を少し捻ったところで、剣先がパンネロの胸元をかすめてしまった。
「あっ!」
パンネロは驚いて小さく叫んだ。本当に、ごく薄くだが、パンネロの鎖骨の下の辺りに10センチほどの傷をつけてしまったのだ。
バルフレアはそれこそ飛び上がらんばかりに驚き、そしてパンネロを傷つけてしまったことを何度も詫びた。パンネロにしてみると、薄皮一枚の話で、3日もしない内にきれいに消えてしまうと思っている。だが大切な大切な恋人に自ら傷をつけてしまったなどと、フェミニストなこの男には耐え難いことなのだ。
「バルフレアったら、たいしたことないよ。」
「錆びた銅の剣だ。」
消毒液をふくませた、きっと高価な物なのだろう、柔らかいハンカチをパンネロの胸元にあて、バルフレアは真剣な顔で答える。
「いいの。とっても珍しい貴重なものなんでしょう?それを真っ先に見せに来てくれたほうがうれしいかったから。」
そんな健気なことを言われると、申し訳なさと愛おしさが同時に胸に湧いてきて、瞬く間に胸を満たした。とにかく、出来る限り最高の手当をしてやらなくては、と、バルフレアはベッドサイドのメモパッドにラバナスタ・ダウンタウンの中のとある屋号の住所を書き付けた。
「いいか、俺が連絡しておく。ここに行って薬をもらうんだ。どんな傷も綺麗に治す魔法入りの薬だ。」
住所を見てみると、地元のパンネロですらめったに入らないダウンタウンの奥の奥だ。大して遠くでもないし、それでオロオロと心配そうなバルフレアの気が済むならと、
「わかった。ちゃんと行ってもらってくるね。」
「わかってると思うが、そこ以外の店の物に手をだすんじゃない。その店はフランが唯一信用している薬師だ。他やつらはどんな物を扱ってるか検討もつかない。怪しい薬ばかりだ。」
「うん、わかった。」
笑顔で頷くパンネロを、バルフレアはきゅっと抱きしめる。
「……ごめんな。」
珍しく落ち込んだ声だ。
「もう気にしないで。ちゃんとお薬、つけるから。」
「何度も言うが…」
「わかってる。他のお店の物には手も触れないよ。」
そう言うとバルフレアは漸くホッとした表情を見せ、そして少し照れたように、
「パンネロは賢い子だから余計だったかな。」
「もう、また子供扱い!」
眉をきゅっと吊り上げるパンネロに、バルフレアはその頬に優しくキスをし、
「俺はしばらくバーフォンハイムにいて離れられないが、それが終わったらすぐに飛んでくる。」
という言葉に、パンネロの機嫌はすぐに直ったのだった。
***********
(あのあとだって、さんざん子供扱い!)
パンネロはちょっとプンプンしていた。本当は一緒に薬屋に行きたいのにとか、あの辺りは危ないヤツが多いからとかなんとか。挙句の果てには、
「ヴァンと一緒に行った方がいいんじゃないか?」
などと言い出したのには本当に呆れてしまった。
(心配してくれるのはいいけど、バルフレアはちょっと過保護すぎ!)
だいたいこんな怪我にも入らないような切り傷でわざわざ魔法入りの高い薬なんて…そうやって怒りながらも、本当に申し訳無さそうに、本当に心配そうにしていたあの顔を思い出すと、その怒りもしぼんでしまって。でも、もやもやした気持ちは胸の中に残って。
(もう…早くお薬もらって帰ろう…)
ラバナスタ・ダウンタウンの奥の奥、カタギの人間ならめったに足を踏み入れないようなエリア。怪しげな薬や素材の露店が軒を並べていて、パンネロはバルフレアの言いつけをちゃんと守って、目的の薬屋を探していた。そんな時だった、その老婆が声をかけてきたのは。
「お嬢ちゃん、占いはどうだい?」
パンネロは一旦足を止めたが、バルフレアの言いつけを思い出し、
「ごめんなさい、急いでるの。」
そう言って立ち去ろうとした時に、
「恋人のことで悩みがあるんだろう?」
そう言われて、思わず足を止め、振り返ってしまった。
「なんでも話してごらん。お代はいいよ。」
そう言われてパンネロは思わずその老婆の店に足を踏み入れてしまったのだった。
***********
潮風に吹かれながら港の桟橋をバルフレアは相棒と2人で歩いていた。フランと次に襲う飛空艇のことを調べている内に、近々バーフォンハイムに停泊するという情報を掴んで、2人でその船が着くのを待っていたのだ。酒場や荷運び人たちからも時々話を聞いて、鉱石と見せかけて実は孤児を売り買いしているその商人たちの飛空艇が着くのは明日の早朝だという所まで情報を絞り込むことができた。
港壁に打ち寄せる波の音や、酒場の喧騒。遠くから聞こえてくる船人の歌は、愛らしい恋人のことを思い出させた。
(港町はいいな…)
次の逢瀬はここにするかと決め、パンネロに何を食べさせてやろうか、真珠と淡いピンクの珊瑚の耳飾りのどちらが好きだろうかなどと考えていると、フランが目配せをした。周りの気配を辿ってみると、誰かが自分たちの後をつけている。
「お粗末な賞金稼ぎだ。」
自然さを装うのが鉄則なのに、こちらを見過ぎているのが感じてとれた。お世辞にも上手とは言えない尾行だった。
「女のようね。」
「じゃ、俺の役目だな。」
付いて来ているのはその女だけのようだ。2人はごく自然に路地に入り、四つ角で左右に別れて別々の方向へと歩く。追跡者は一瞬躊躇したが、バルフレアの後について来た。細くて狭い路地の角をいくつか曲がったところで待ち伏せると、女は容易くバルフレアの胸に飛び込んできた。
バルフレアは身体を反らせ、それを避けると女の背後に回り込み、腕をねじり上げて壁に押し付けた。見ると、女はラバナスタの踊り子の衣装を身に着けている。
「これはこれは。俺のことをよく勉強しておいでだ。」
バルフレアにはパンネロのことと、パンネロとのことを見知らぬ誰かに触れられるのを何よりも嫌う。これは彼にとって逆効果の最悪な演出だ。
「女だてらに賞金稼ぎか?だが、相手が悪かったな。」
腹が立って、より一層腕を強く捻ると、女が小さく悲鳴をあげた。
「命までとは言わんが、骨の一本は折らせてもらうぜ。後を付け回されるのはごめんでね。」
折ると言われて押さえ込んでいた女が身を捩って逃げようともがく。
「暴れると余計に痛いぜ。」
「ば、バルフレア……っ!」
名前を呼ばれ、バルフレアは驚いて手を止めた。
「その声は……パンネロ……か……?」
壁に押し付けた手の力が緩んだせいで、肩越しにパンネロが振り返る。よっぽど強く腕を締めあげられていたのだろう、痛みで目尻に涙が浮かんでいる。バルフレアはその表情に釘付けになった。涙ぐんだ瞳が扇情的とかそんな理由ではない。だが、間違いなくその顔に惹きつけられ、目が離せなかったのだ。
短く切り揃えられた前髪はいつの間にか長く伸びて真ん中で分けられ、いつも前髪の下から顔をのぞかせていた額は長く伸びた前髪の間からきれいな三角形を描いてその姿を顕にしている。ゆるく編まれたおさげは解かれ、編まれていた部分がウェーブとなって背中を覆っている。おまけに、背伸びをしたいお年ごろのパンネロは、控えめではあるがバルフレアに会う時は頑張って白粉をはたき、瞼の縁に線を引き、口唇に濡れたような紅をさしてくるのだが、今日はいささかそれが濃すぎるような気がする。
バルフレアは暫くパンネロの顔を見つめていた。確かにパンネロなのだが、単にいつもよりも化粧が濃いとだけでは説明できない違和感があった。まず、化粧が化粧のようには見えないのだ。ごく自然に顔に馴染んでいる。何よりも髪だ。ベッドの中ではもちろん髪を解くので、パンネロの髪がどれくらいの長さなのかバルフレアはよく知っている。むしろ、自分とパンネロしか知らないというのが自慢なほどだ。なのに、目の前のパンネロの髪はいつもより長いのだ。肩甲骨を覆うほどの長さが、今は腰にまで届いている。
「本当に…お前なのか……?パンネロ?」
信じられない気持ちと、警戒を解くのは早いという声が同時にする。誰かがパンネロに化けて自分を襲ったのではないか、だが目の前にいるのは間違いなくパンネロだという確信もあって。
「バルフレア……私……」
声も確かにパンネロなのだが、いつもの少女らしい少しハスキーな声が、鼻にかかるような甘ったるい物に変わっていて、こんな時なのに涙ぐんだ瞳とその声が下半身を直撃するようだ。だが、そんなことよりも異常事態だ、と頭の中で警報が鳴る。目の前に居る女は本当にパンネロなのだろうか?万が一ということもある、何か証明する方法はないかと考えたところでひらめいた。
(傷だ……)
昨日、誤って自分がパンネロにつけてしまった傷、それがあれば間違いなくこれはパンネロということだ。バルフレアは腕をねじり上げたまま女の肩を抱き、自分の胸に引き寄せるようにしてこちらを向かせた。女の顔がすぐ間近に来て、バルフレアを見上げた。
バルフレアは息を呑んだ。確信した。これは化粧で変わった顔ではない。すっと切れ長な瞳はそのままなのに、まばたきをする度にぱちぱちと音が聞こえてきそうな濃いまつ毛が瞼に濃い天然のアイラインを引き、同時に瞳に蠱惑的な影を落としている。何も塗らなくても花びらの様に桃色をしていた可憐な唇は、今はぽってりとした滑らかなボリュームを持ち、僅かな月明かりすら照り返し、艶やかに濡れて輝いている。心細げに自分を見上げるその表情がまた官能的だった。バルフレアはまるで時間が止まったかのようにパンネロの顔を見つめていた。
とにかく、これがパンネロでないか確かめないと、と胸元に目を落とし、バルフレアは絶句してしまう。細い顎、首、華奢な肩はそのままだ。
(なんだ…これは……!?)
華奢なパンネロは胸のサイズが秘かにコンプレックスだった。“私、子供っぽくないかなあ”と漏らす時は決まって肉感的な女性とすれ違った時だ。だがそれが今はち切れそうに白い上衣を押し上げ、盛り上がった半球が上衣の縁からはみ出て、こぼれ落ちそうだ。
それがバルフレアに魅力的でないわけがない、このままパンネロを抱きしめ、その口唇を奪いたいと強く思った。が、その欲求を押さえ付けたのは胸元に残った、自分がつけてしまった傷あとだ。それを見てバルフレアはすぐに何が起こったかを察した。大人になりたくて仕方がないパンネロ、ダウンタウンの怪しい薬屋は口がうまい。言葉巧みに客をぺてんにかけ、怪しげな薬を売りつけるのだ。
「パンネロ!!」
バルフレアはパンネロの肩を強く掴み、怒鳴った。自分でも驚く程の大きな声だ。パンネロに声を荒らげたことなど一度もなかった。だが、その怒りを制止できなかった。何かを使って自分の身体を作り変えてしまうことは、この男にとって、もっとも忌むべき事柄だ。
案の定、パンネロはびくりと肩を跳ねさせ、ぎゅっと目を閉じてしまう。どうしようもなく腹が立った。パンネロに薬を売りつけたいかさま薬師どもを片っ端から地獄に叩き落としてやりたい程だ。そうして、いくら山場を控えていたからといって、そんな所にパンネロを一人で行かせてしまった自分にもだ。
バルフレアは気持ちを落ち着かせようと大きく息を吐いた。だが、それはパンネロにはバルフレアが自分に魅力がないものだと思わせてしまい、悲しくなり涙ぐむ。怒りのあまり言葉が出てこないバルフレアに、パンネロは後ろめたさから問われもしないのに何が起こったかを話し始めた。
「ダウンタウンの…お薬屋さんに行こうと思ったの……そこで、占い師のおばあさんが……何かお悩みかい?って。」
「それで口車にのせられて、ワケの分からない薬を買って飲んだのか!?」
「……お代は後でいいって……」
「それがアイツらの手だ!!」
バルフレアが大声を出すのに、泣き出しそうに顔を歪めていたパンネロは顔を伏せ、ついに声を殺して泣き始めた。
「……私……キレイじゃ……ない……?」
まるで大輪の花が萎み、首を垂れているその様は、胸をしめつけられるほどの儚げさで、バルフレアの胸も激しく痛んだ。
「私……バルフレアに見せたくて……」
「……そんな姿が本当にきれいだと思うなら、お前はどうかしてるぜ。」
バルフレアは吐き捨てるように言ってパンネロの言葉を遮ると、手を強引に引っ張った。パンネロが泣いているのは分かるが、今は優しくしてやれそうにないし、また、優しくしてはいけないとも思うから声はかけないでおく。
合流場所に成長したパンネロを連れて現れたバルフレアに、フランは驚いて目を丸くしていた。が、すぐに泣いているパンネロを優しくなだめ、何を飲んだかを問いただし始めた。フランに優しく諭されて気持ちが少し落ち着いたのか、パンネロは泣きじゃくりながらも飲んだ時の味、色、香りに温度を伝えた。それを聞いて飲まされた薬は効果は持続しないし、依存性のあるものではない、とフランは判断した。
「おそらく成長を促す化学薬品に適当な薬草で味と香りをつけ、効果を何倍にも増幅するよう魔法をかけた物ね。」
「本当か!?」
「大したことないわ。明日には元に戻ってる。副作用があるとしたら……」
「副作用があるのか!?」
「そうね、あったとしても、気持ちが不安定になるとか、あとは少し湿疹が出たりするくらいね。」
「もうとっくに不安定だ。」
バルフレアが横からイライラしたまま口を挟むのに、パンネロも遂に我慢していたものが爆発する。
「だって!バルフレアがいつも子供扱いするからでしょう!?だから私…!!」
「だから怪しい薬師で騙されて、おかしな薬を飲んで大人になりましたっていうのか!?」
「そんな言い方…!!だって…!!」
「じゃあ聞くが、俺がいつお前に早く大人になれと言った!?」
パンネロはとうとう手で顔を覆い、わっと泣き出してしまう。フランはやれやれ、とため息を吐いた。基本的に2人のことには口は出さないし、バルフレアもそれを弁えていて、こんな痴話喧嘩に巻き込まれるのは始めてのことだった。仲裁するつもりもないが、かと言ってバルフレアもパンネロも平常心ではない。
「今日はもう帰りなさい。大丈夫だと思うけど、部屋で大人しくしているのよ。」
目をゴシゴシと擦る仕草は16歳のパンネロそのままだ。
「…せっかく来たのに、キスもしてくれないの……?」
「大人だったら、一人で帰れるだろう。」
「バルフレア…」
フランにたしなめられ、バルフレアはチッと舌打ちをして背を向け、それきりパンネロを見ようともしなかった。パンネロは泣きながら市場を抜けた先にあるテレポクリスタルの方に走っていってしまった。
「本当に送らなくて良かったの?」
「子供扱いが不満なら、甘やかすのはお門違いだろ。」
「甘えたい恋人には逆効果じゃない?」
「何が言いたい。」
パンネロがちゃんとテレポクリスタルの方に走って行くのを見届け、フランは漸くバルフレアの顔を正面から見た。
「そうね。恋人としては逆効果だけど、父親としては正解ってところね。」
「誰がだ。」
面白くなくて、バルフレアは目の前にある空の樽を蹴飛ばした。
「明日は予定通り?」
「もちろんだ。ただ…」
バルフレアはムッとした顔つきのまま、不愉快そうに言い捨てた。
「次の獲物は、俺たちに襲われたことを後悔することになるだろうがな。」