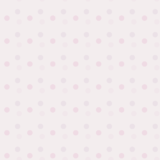この記事を読むのに必要な時間は約 16 分です。
唇を押し付けてはまた重ねる。角度を変えそれを何度も繰り返しているうちに、エドガーの頬に朱が差し、眉がきゅっと寄せられた。口唇が離れたわずかの瞬間に苦しげに息を継ぎ、それが塞がれると素直に舌を差し出す。
「…さっきの薬に何を混ぜた?」
「知ってるのだろう?」
囁きながら耳の中を舌でねぶる。エドガーはそれだけで腰を跳ねさせ、大きく喘いだ。
「…っ、いった…い、どんな…本だ…」
「今度見せよう。作って貰いたいものもいくつかある。」
「お互いに楽しむため、か?」
「愛してるからさ。」
ヴェインの唇が再び耳朶を這う。濡れた舌先は耳殻をくすぐり、にちゃにちゃと音を立てた。ぞくりとした感覚がそこから湧いてくる。愛してると言ってくれたのだ、ならばいつも自分が言うようにお互いに楽しもうと、エドガーは唇から堪えることなく息を漏らした。口移しで与えられた回復薬には性感を高める物が含まれていたのだろう、身体はあっけないほど簡単に芯から熱くなった。
ヴェインはエドガーのの髪を解き、髪の間に指を滑らせ、梳く。もうそれだけで下腹辺りに熱が集まり、早くも行き場を求めた灼熱が、閉じられた窪みの中で蓋を押し上げようとするのに、エドガーは喉を鳴らした。
「力を抜いてくれないか、エドガー。」
尋ねてはいるが、どこか尊大な頼み方だとエドガーは心のなかで思う。何か軽口を叩こうと思ったが、ヴェインの瞳が冷たいものではなく、かと言って優しくもないのだが、
(…これは…どういう………?)
今まで見たことのない表情を見せられ、エドガーはその目に釘付けになる、と同時に針がさらに奥へと挿し入れられた。
「………っ、く…ぅ…っ!」
思わずうめき声を上げたエドガーを宥めるようにヴェインは胸の中にあるエドガーの頭を優しく撫でてやる。ほんの1cmほど奥に差し込んだだけで、官能はあっという間に散ってしまい、あのいやな汗が背中を伝った。
すぐにヴェインが触れるか触れない程度に優しく亀頭部を撫で始めた。刺された針のごく狭い空間を通って先走りの液が湧き始める。それだけでもう爆発しそうな射精感に襲われ、エドガーは腰を悶えさせた。
「ヴェ…イン……」
「取ってくれ、という懇願なら聞く耳はもたない。」
そう言うと、針をまた軽い力で揺する。
「は…ぅ…!ぁ……っ……」
強過ぎる刺激に鈴口から湧く透明の粘液がとろとろと溢れる。
「だが、睦言として聞くなら悪くはないな。」
ヴェインは指先でエドガーの陰茎から溢れる液を掬い取ると、反対側の手でエドガーの腰を少し持ち上げ、手をその奥へと伸ばした。きゅっと窄まってる後孔にその液を塗りつけ、撫でられると、じわじわとむず痒いような感覚がそこから広がった。咄嗟にエドガーは激しく頭を振ってその感覚を散らそうとする。それは拒絶ではなく反射的なものだと知っているヴェインはそのままゆっくりと指をそこに埋めていく。
「あ…ぁ、ヴぇ…イン……」
苦痛と快楽で聡明な美貌は手のひらで握りしめられた花のように無残に歪められているのに、ヴェインはその顔を見れば見るほど愛おしいと感じてしまう。
「あっという間に私の指を飲み込むようになったな。」
「…喜んでもらえて、うれしいよ…」
「自分でもしていたのか?」
「まさか。」
そこまで不自由はしてないさ、とこんな時でも笑ってみせるエドガーの言葉に、ヴェインはどうしてだか胸が踊るようなうれしさを感じてしまう。
(その悦びを、今は受け入れよう…)
このところのエドガーとの関係を、そして自身の気持ちを明瞭な頭脳でもって考えてみたのだ。これは恋ではない。だが、この男の言う通り同じ魂を持つのなら…もし、そんなものがあるとしたならば、一度くらいは自分の気持ちを偽らなくても良いのではないかと思ったのだ。侮蔑でもない、媚びるのでもない。不可解だが心臓が時折早く打つのも、逆に重く、息苦しくなるのも、エドガーがもたらすものならば、この男が言うようにそれを楽しむことにしたのだ。
「光栄だな。私が初めてだったのか?」
「君がうれしいと、私もうれしいな。」
「力を抜いてくれ。」
エドガーもなんらかの気持ちの変化がヴェインの中に生まれたのに気付いていた。彼とのやり取りは初めての頃と比べると穏やかに、それこそ恋人同士のように響くことすらあるのだが、
(…この針さえ、なければ…ね…)
そうして、エドガーは身体の力を抜くために大きく息を吐いた。
「いいぞ。」
ヴェインがくい、とわずかに中指を曲げただけでエドガーはうめき声をあげて仰け反った。
「そのまま、ゆっくり息をしていてくれ。」
今までの一方的な行為とは違う。まるっきり違う。エドガー自身も、それが何故だかうれしい。もちろん、針には閉口しているのだが、かつてベッドを共にした女性たちとは味わったことがない胸の高鳴りだった。だが、それを素直に告げるような間柄でもないと思い、その気持ちは大事に閉じ込めておくことにする。
「随分とためになる本だな…」
代わりにそんな軽口を叩くが、ヴェインは答えなかった。エドガーが息を吸い込むのを待って折った指先で指先に当たった所をぐっと押す。エドガーはそれだけでぶるっと全身を震わせた。
「どうだ?」
「…聞くのは野暮だよ。」
ヴェインがくっくと笑う。
「そのままだ。ゆっくりと吐いて。」
エドガーは言われたままゆっくりとした呼吸を繰り返す。息を吸うタイミングで前立腺の裏側をぐっと押され、息を吐くと力を緩める。呼吸の度にどんどんとそこに快感が溜まり、上り詰めていくのが分かる。それは絶妙で素晴らしく、自分が鎖で繋がれていることなど忘れるほどだった。反面、時折針でとても細いその道を金の針でかき回されると、文字通り刺すような強い快感が狂おしいほどの絶頂感を促すのだが、不粋な針にそれをせき止められ、エドガーはじれったい感覚に悶えた。まるでとてつもないエネルギーを持った生き物が自分の下腹の中に潜り込んで暴れてるようで苦しい。それを取り出さないと、きっとそれは自分の腹を蹴破って出てくるのではないかと思うほどだ。
「…ヴェイン…!ヴェイン…!」
懇願してもヴェインが針を取るつもりなど毛頭ないのはわかっている。それでも、強すぎる快楽にまる脳髄まで焼かれたようで、エドガーは何度もヴェインの名を読んだ。
不意にヴェインがぷつんと勃ち上がったエドガーの胸の突起をそっと歯で噛んだ。
「んっ…!…んっ……う、ぁあっ……!」
それはエドガー本人ですら予見していなかった。腰がブルっと震え、そして呻き声を上げて、エドガーは腰を跳ねさせた。歯をきつく食いしばり、まぶたをぎゅっと閉じ、両の太腿もヴェインの手をきつく挟み、そのまま何度も腰を跳ねさせた。
「あっ…あ、ヴェ…イン…っ…!」
身体をひくひくと痙攣させ、飲み込めなかった唾液が口の端から滴り落ちた。ヴェインはそれを舌先で舐めとってやる。
「射精せずに達したか…」
「……これが、”楽しみたかったこと”……か……」
肩で息をするエドガーにヴェインは満足気に頷くと、達することが出来ないままビクビクと跳ねまわるエドガー自身に手を添えた。
「あ…ぅっ!」
エドガーは悲鳴を上げ、背をしならせた。ヴェインは握りしめたエドガー自身をそのままゆっくり扱きあげながら、後ろに入れた指でくちゅくちゅと音を立て、エドガーの後孔から壁越しに触れる快楽の源泉を刺激し続ける。エドガーが狂ったように暴れ、頭上の鎖がガチャガチャと耳障りな音を立てるが、ヴェインにとってはそれすら心地よく耳に響く。
「…最高だ、エドガー。」
叫び声を上げ続け、先端から溢れる液は陰茎をつたい、大きく開かれた足の付け根まで濡らしていく。
「……ヴェ…イン……ま、た……」
「すごい締め付けだ。指が千切れそうだな。」
心なしかヴェインの声が弾んでいる。そして、今度は握りしめたエドガー自身のくびれた部分を親指でぐい、と強く擦った。
「っ……くぅ…ぅ…っ!」
腰を前に突き出すようにしてエドガーは2度目の絶頂を迎えた。吐精を許されず、針を刺されたままの男根は獲物に襲いかかる蛇の様に激しく暴れまわる。が、精液を吐き出すことは叶わず、透明の液をドクドクと針を刺された隙間から流し続けるだけだった。エドガーはもう身体を動かすことも出来ず、鎖に吊るされたまま肩を大きく上下させている。達したというのに、未だに熱の塊が下腹で早く出せと言わんばかりに暴れまわる。
「……ヴェ…イ…ン……も、う……」
ヴェインはエドガーの懇願を聞き流し、さらにエドガーの中に埋めたままの指で探し当てた秘密のその空間を強く押した。
「はぁっ……んんっ……っ!!」
まるで雷に打たれたようにエドガーの身体はびくびくと何度も跳ねた。強すぎる快楽が背筋を駆け抜け、だがそれは身体の中にくぐもったまま膨らみ続けるのだ。苦しさに暴れ、鎖を引きちぎろうとしていたエドガーだが、それが叶うはずもなく、やがてぐったりとうなだれた。
「ヴェイン……出…させ…て…くれ……」
「…エドガー……」
「もう……苦…し……」
ヴェインは弑逆的な笑みを浮かべると、後ろに入れたままの指を乱暴に引き抜いた。
「うっ、あぁあぁぁ……っ!!」
引き抜かれるその感覚に、エドガーはたったそれだけで何度目になるか分からない絶頂を迎えた。仰け反り、喉を開き口を大きく開き、痛みと悦楽に悲鳴を上げながら再び崩れ落ちた。
「……いささか、やり過ぎた…か。」
ヴェインは上着の内ポケットから鍵を取り出すと、頭上で括られている鎖を外し、崩れ落ちてきたエドガーの身体を受け止めた。そのままその身体を横たえると、先端に刺したままの針をゆっくりと引き抜いた。
「……う……」
その刺激でエドガーが目を覚ました。とろん、とした目でヴェインを見上げる。
「…ひどい…な……」
「素直に詫びよう。」
エドガーはゆっくりと腕をヴェインの首に巻きつけた。
「金でないといけないのは…医療器具と同じだな。銀や鉄だと中が傷ついた時に炎症を起こす。」
「読んだことがあるのか?」
「機工士だからね、私は。」
太ももの裏側に手を入れられ、持ち上げられた。
「君の心遣いがうれしいよ。」
「あまり言うな。」
「いけないかい?」
「照れる。」
端的に言い捨てると、ヴェインは下衣を手早く脱ぎ、まだ快楽の余韻にひくついている蕾に熱く滾った陰茎を押し当て、ぐっと押し入れた。慣れたと言っても挿入は未だ苦痛を伴い、エドガーは低く呻いた。しかし、ヴェインは容赦なく根本まで己自身を深々と突き立て、ゆっくりと抜き差しを始めた。
「く……う、ぁあ…あ……」
何度かの抜き差しのあと、次第に痛みが遠退いてくる。ヴェインはエドガーの身体からふっと力が抜けたのを感じると、腰を引き、ぐっと力を入れて自身を入れなおしてきた。
「うっ……ぁっ……」
さっき指でさんざん弄られた箇所を、しなやかな先端で抉られ、エドガーはその気持ちよさに声を漏らした。そこから蕩けそうな快感が溢れてくる。
「ヴェ……イン…!ヴェイン…!」
さっきまで閉じられた道をこじ開けるようにすすんでいたヴェインの肉の楔が、今では滑らかに出入りを繰り返し、それは穿たれる度に的確にエドガーの最も感じる場所をぐりぐりと突いてくる。最初に、長い間せき止められ、吐き出すことを許されなかった欲望が弾け、2人の腹の辺りをべっとりと濡らした。
「ふ……ぅ、ぁあ…あ……」
漸く苦しい責めから解放されたエドガーを、ヴェインは優しく抱きしめた。エドガーはヴェインにしがみつき、はぁはぁと忙しない息をなんとか整えようとする。
「わ…たし、の乱れた姿は君にはそそらないようだ…な。」
ヴェインの男根は未だにエドガーの中でその剛直を保ったままだ。
「いや、限界だ。」
思わせぶりにエドガーの首を撫でていたヴェインだが、すぐさまエドガーの口唇を塞いだ。お互いの舌をねぶり合い、唾液を飲み干す。
「……動くぞ。」
エドガーが何かを言う前に、ヴェインが大きく腰を突き上げた。ずんっと重い衝撃が下半身に響いた。繋がった所からは水音がにちゃにちゃと響く。ヴェインがエドガーをきつく抱きしめた。ヴェインをを咥えこんだ蕾が絶頂の予兆にひくつき始め、ヴェイン自身もその中でぐっと質量を増した。律動が激しくなる。
「くっ……は、ヴェイン……!」
その抽挿は理知的な執政官、冷徹なソリドール家の跡取りとしての面影はなく、さながら野生の獣のようだった。欲望を露にしたヴェインに組み敷かれ、エドガーはさっき見せたヴェインの表情をふと思い出した。
(そうか…)
背中に回した腕に力をこめる。あの時見せた怒りでも優しさでもないあの表情。
(あれが、ヴェインか…全ての殻を、取り払った…)
それに気付いた途端、圧倒的な力の差で屈服させられ、自分にのしかかり、まるで女のように辱めていたヴェインがたまらなく愛おしく、そして哀れに思えた。意識も身体も快楽に蕩けて何も考えられなくなっているのに、その一点だけは頭は澄み切っていて。
ヴェインの気持ちを知り、自分の気持ちを知ったからにはもう今まで通りでは居られないだろう。いや、居てはいけないのだ。友人として同じ魂を持っていても、その相手よりも守らなければならない物があるのならば。
(さよならだ……)
涙が零れそうになったその時、意識がふっと宙に舞った。ヴェインが放った奔流が注ぎ込まれるのに任せ、互いが互いを強く抱きしめた。
*****
その後のことはぼんやりとしか覚えていない。その後数えきれないほどキスをして、何度も交わい、気が付くとヴェインは居なくなっていた。横たわった石の床が冷たくて、さっきまで愛し合っていた冷徹な恋人の体温が無性に恋しかった。視線を巡らせると、さっきの淫らな戯れに使われていた金の針が落ちていた。手を伸ばそうとして、改めて手枷が外されたままなことに気が付いた。
「…ヴェイン。」
エドガーはごろん、と仰向けになって天井を眺め、両手で顔を覆い、慟哭した。ここは誰も居ない。ヴェインすらだ。だからこそエドガーも自分の気持ちを吐露することが出来た。ヴェインはまるで滅び行く城で一人で最後まで旗を振り戦う騎士のようだと思う。超越した存在に反旗を翻し、幼い弟のために手を汚し続けてきたヴェインはエドガーにとって王としての気高さと哀しさを身をもって体現した存在だ。
「…私は、君だよ。」
私が君なら同じことをしていたさ、エドガーはそう呟くと、手の甲で涙を拭って立ち上がった。屈んで、指先で金色の針をつまみ上げる。
「それにしても…私を苛んで、辱めた針を使って出ていけどは、君も趣味が良いな…」
エドガーはそううそぶくと、ヴェインが残した金の針に愛おしげにキスをした。
おわり。