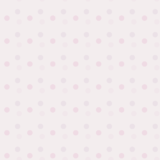この記事を読むのに必要な時間は約 19 分です。
- 男性同士のセックスです。
- ハッピー・エンディングではありません。
物語の背景
- ヴェイン、フィガロの機械技術を狙ってエドガーに接触。
- 友好的な態度で近づき、友情のようなものが芽生える。
- しかしヴェインは隙を突いてフィガロを攻略→征服
- 囚われたエドガーは牢の中
その鉄の扉の入り口には通常の錠と、それに追加されたものが3つ、不格好なつっかえ棒が扉の上部、真ん中の辺りと、さらに下の方に3本、加えて魔法で封印が施されている。
こんなやっかいな囚人はいないなとヴェインは思う。
まず一日おきに部屋をうつさなくてはならない。そのあと、清掃と称して牢の中を徹底的に探査する。どこかに怪しげな道具を隠していないか、いつの間にか抜け道を作っていないかを、人力と魔法の両方でだ。
そこまでさせても疑心暗鬼は拭えない。機工士を閉じ込めておくのは至難の技だ。スプーンやナイフ、着替えのズボンの紐、そんなものでまるで奇跡のような脱出装置を作り出すからだ。
いくつもの鍵を開けさせ、封印をとき、人払いをして扉を開けると、フィガロ国王で、今は アルケイディア帝国の囚われ人であるエドガー・ロニ・フィガロ微笑みながら自分を迎え入れる。
高貴なのに人を惹き寄せる男だ。小さな、だがとても進んだ技術を持った国の国王だ。民を愛し、民に愛され、仲の良い双子の弟がいると話していた。ランプやろうそくの類はもちろん厳禁なので天井のすぐ下にある明かりとりの窓から星の光がわずかに石畳の部屋を照らす。それなのにその男の髪は薄暗い部屋ですらまぶしいと思わせるほど輝いていて。
「やあ、よく来てくれたね。」
思ってもいないことを、と思う。だが、もう考えるのは止めたのだった、ということを思い出し、粗末なベッドに腰掛けた男にのしかかった。真上から見下ろす時、ようやく目と目があって、お互いを見つめ合う。聡明そうな広い額、まるで希少な宝石のように深く蒼い瞳を髪と同じ金色の睫毛が縁取っている。その目元から完璧な弧と角で描かれた鼻筋。しかし、輪郭は女性のそれとは違い、がっしりとした頬骨とあごのライン、それでいて均整がとれていて。どこをとっても正しく美しい、端正な顔だ。牢での生活でも少しも色褪せていない。
「君が来てくれるのはうれしいが、いつも扉を開けるのが大変そうだ。お付の者たちに申し訳ないよ。」
答えるのが面倒で、弾力のありそうなその口唇を塞いでしまう。その時、目を閉じ、眉をきゅっと寄せるその瞬間に背中がゾクゾクとした感覚が駆け上がる。自分はこの美しい顔をこうやって歪ませることに耐えようもないほどの興奮を感じるのだと気付いたのは初めてこの男を陵辱した時だった。痛みと屈辱で歪む顔は自分をどれほど昂らせるのだろうと思ってねじ伏せてみた。さほど大した抵抗もなく、苦痛に顔を歪めながらもその男は自分を受け入れたのだった。
「…っ…、…」
息苦しさのせいか、男が小さく呻いた。
口唇の弾力というのは男も女もさほど変わらないな、と思いながら今度はその口唇を割って舌を潜り込ませる。女を抱いている時と同じ手順で首筋を撫で、鎖骨、胸骨を辿り、左側の胸の辺りをまさぐる。この辺りから自分は男を抱いているのだと思い出す。
最初の頃はそれでも侮蔑するような言葉を最中に投げかけたこともある。欺かれ、国を支配された憎むべき相手に、恥とは思わないのかと。だが、
「折角の機会だからね、楽しもうと思ったんだよ。」
「楽しむ?」
「素敵なレディ達と楽しむのとはまた違うよ。男同士、というのは存外気楽で良いものさ。」
「楽観的にもほどがあるな。」
「誰にでも、というわけではないさ。」
そう返されて、それが無駄だと悟ったのだ。
脂肪ではなく筋肉で盛り上がった胸の辺りを撫でてみる。こんな所を撫でたところで何も感じはしないだろう。何も感じないだろう、と思っていたのが、時折大きく息を吐くのでそれなりに良いらしい。半ば瞳を閉じで、ぼうっとした表情だ。
一応元国王ということで、エドガーが着ているのは囚人服ではなく、白いシャツだ。それをはだけ、左側の袖だけ剥がし、現れた胸板を見る。女性の円すい形の胸とは違い、盛り上がってはいるものの男の胸は平らだ。実を言うと最初はそれすら混乱したのだが、今では女の所に通うよりもこの独房に来ることの方が多いのでもう慣れた。
滑らかで硬い弾力のある胸をまさぐる。これはこれで手に返ってくる弾力が心地良い。何よりもエドガーが肩で息をし始め、胸が大きく上下し始めたのが痛快だ。
空いた方の手でもう片方の袖を抜くと、上半身が顕になった。きっと女が見たらため息を付き、もしくは嬌声を上げるであろう彫像のような美しい身体だ。筋肉は皮膚を盛り上げて胸板と腹筋にくっきりとしたコントラストを築き、胸板は厚く、無駄な体毛もない。
首筋に舌を這わせ、胸板の上でプツン、と尖ったその先端を指で転がしてみる。
「……っ…」
押し殺した声が漏れ、美しい顔をシーツに埋めてしまう。それを追いかけるようにして、その顔をを覗き込む。そうだ、この顔が見たいのだ。男でも乳首はやはり性感帯だ。舌でも愛撫すればもっと感じさせることが出来るのだろうが、そうするとこの高貴で端正な顔が歪むところが見られないではないか。
ヴェインは膝立ちになると、両手で肌に溶けるほど淡い色をしているその先端を同時ぎゅっと強く摘んだ。
「…ぅ…、は…っ」
さすがに声がこらえ切れないようだ。そのまま親指と人差し指で扱き上げる。
「く…っ…」
その声にもっと酔いたいと、摘んだ乳首を少し引っ張ってみる。
「う……ぁ、…ヴェ…イン…」
自分の名前を呼びながら、喉を開き、頭を仰け反らせた。そうだ、その表情、その声だと中指も加えて執拗に小さな乳首を攻める。今度は身体全体が跳ねた。
「…、少……し…痛い…よ、ヴェイン…」
咎めるような声。たまらない。お構いなしにもっと強く引っ張り、親指の腹と人指し指と中指を敏感なそこにぐりぐりと擦り付ける。今度は苦痛に目をぎゅっと閉じ、歯を食いしばる。
「…指、よりも……ここに、キスしてくれた方が…うれ…しいな…」
知るものか、と構わずひたすら擦り、扱く。
「ヴェイン……」
奥歯を噛み締め、その合間に懇願してくる。だが自分は恋人でもなんでもないのだ。相手の意向を汲む必要はない。そんな時、つとエドガーがの手が伸びてきて、ヴェインの股間に触れた。自分でも気がついていなかったのだが、そこはすでに熱を持ち、固くなっていた。思わずヴェインの手が止まる。
「…不粋なセックスは…好きではないな…」
「虜囚の身でよく言う…」
不敵な獲物にヴェインは口を歪めてクッと笑う。
「関係ないさ。いかなる状況でも、お互い楽しむのが私の挟持でね。」
「たとえ牢の中でも…か。」
その通りだ、とエドガーは手を伸ばし、ヴェインのシャツの釦を外す。ヴェインはその手を払いのけ、自ら釦を外し、シャツを脱ぎ捨てた。すると、エドガーはすぅっと目を細め、その体躯を見つめる。
「…なんだ?」
「美しいな、君は。」
「…媚びた所でここからは出さん。」
「本当のことさ。」
エドガーは身体を起こし、ヴェインの顔を正面から見据える。
「哀しい物語が美しいように、君は美しい。」
「いい加減にするがいい。」
ヴェインはエドガーの顎を強く掴んだ。
「憐れんでいるのか、私を?」
静かだが普通の人間なら震え上がるような低い、迫力のある声だった。
「愛してるよ、ヴェイン。」
「悲劇の芝居を愛でるように、か。」
ヴェインは手を離すと同時に、エドガーを身体ごと組み伏せる。
「少し違うな。」
エドガーはヴェインの背中に手を回し、優しく撫でてやる。エドガー自身も、撫でているヴェインの背中を女性とは違うな、と考えながら。
「ヴェイン、私はまだまだ若輩者だ。フィガロにも権力争いはあった。だが、君のように兄弟を手に掛けるようなことにならずに済んだ。」
エドガーは尚もその背を撫でる。
「機工士としては誰にも負けないつもりだ。だが、政治手腕は君には及びもしない。」
実際、君にはあっさり占領されてしまったしね、とエドガーは笑う。
「だが、君に捕らえられ、こうやって身体を重ねていて一つ分かったことがある。」
決して自嘲的でもなく、ヴェインに媚びる感もない。なので、ヴェインはついその言葉に耳を傾けてしまう。
「私は君で、君は私だ。」
「小国の分際で…」
「そんな野暮は言いっこなしだ。私とて、すんなり王になったわけじゃないからね。」
エドガーは今度はヴェインの頭を撫でてやる。時折、指に髪を絡め、優しく。
「君は悲劇の主人公だ。悲劇は美しい。どうしようもなくね。誰にも止められない。誰にも救えない。だから美しいのさ。」
「…誰にも…救えない…か。」
「だから楽しもう、と言っている。」
耳元に秘密を打ち明けるようにエドガーが囁いた。
「これは恋ではない。愛でもない。不毛な魂の共鳴だ。ただ、痛いだけの…ね。」
「何も生み出さない、君に私は救えない。お前の命は私の手の中…」
ひとりごとのようにヴェインが呟いた。
「ただの共鳴さ。」
「磁石のようにか。」
その喩えはロマンティックではないな、とエドガーは笑った。
「そうだな、月と、私達の住むこの星のように、さ。同じ距離を保っているが、決して互いが互いを離すことはない。」
「気取り過ぎだ。」
ヴェインは漸く身体を起こし、エドガーの顔を見据えた。
「脱出の機会をうかがっていて、互いを離さないと言って信用できるわけがない。」
エドガーがおかしそうに笑う。そうしてヴェイン自身、今までこんな雰囲気を味わったことがない、と気付いた。エドガーの”楽しもう”という提案も満更ではなく思えてきて。
「続きをしてくれないのかい?」
エドガーの言葉に物思いに耽っていたヴェインは我に返った。エドガーが背中に回した腕に力をこめたせいで、胸と胸がしっかりと合わさり、その肌の温かさに心地よさを覚えた。腰をが密着すると、腿の付け根の辺りに熱く硬いものが触れ合った。互いの身体を強く抱きしめ、その間に腕を潜り込ませて互いの股間を揉みしだく。
ヴェインは身体を下にずらし、エドガーが履いている粗末なズボンを下ろした。そして下着をその形のままくっきりと盛り上げている陰茎を布越しに舌でなぞった。
「…っ……く……」
下着をずり下ろすと、飛び出してきて塊をヴェインは手に取り、先端を手のひらでぐるり、と撫で上げた。
「…、ぅ…っ…」
いきなり敏感な先端を強く刺激され、エドガーの身体が跳ねた。ヴェインは溢れている先走りの液を手のひらに塗りつけ、そこからエドガー自身を握り、片手で上下に扱き始めた。ぬちゃっと湿った音が部屋に響く。それと同時にエドガーの口から切なげな息がこぼれた。
「…は……ぁっ……」
エドガーは時折快感にぶるりと身体を震わせ、その度に先走りの液が先端から溢れ、茎を伝い落ち、ヴェインの手を濡らした。濡れた手で猛った男根を扱くと、その液が全体に塗り込められ、手の動きをますます滑らかにする。
「ヴェイ…ン……」
限界が近いのはすぐに分かった。握りしめたエドガー自身はびくびくと脈打ち、鈴口が、まるでそこで息をして喘いでいるかのようにひくひくと収縮を繰り返しているからだ。
「私を愛している、と言ったな。」
ヴェインはまた口の端を歪めるようにして笑った。
「私も、愛しているさ、エドガー。私なりにな。」
そう言うと、エドガーが着ていたシャツを手に取り、袖の辺りに歯を立て切り裂いた。そしてその切り裂いた袖でいきり立つエドガー自身の根本をきつく縛った。エドガーは苦しげに眉を寄せる。
「…君の愛…か、うれしいね。」
「エドガー…私は、君の顔を歪むのを見ると、どうしようもなく昂ぶるのだ。」
「サディスティックな愛だな…」
ヴェインはエドガーの腕を引き、身体を浮かせると、浮いた身体の下に腕を回してうつ伏せにした。
「愛しているよ、エドガー。」
「だったら、どうかお手柔らかに頼むよ。」
「腰を上げてくれ。」
エドガーは言われるままに腰を浮かせる。うつ伏せになり、伏せられた顔の周りを金色の髪が彩る。ヴェインはエドガーの背中を抱えるようにして身体を合わせ、エドガーの足の付根から血管を浮かせ、びくびくと震えているそれをきゅっと握り、揺らすようにしながら扱き始めた。
「…ん、……くっ……」
こみ上げてくるモノを吐き出せず、エドガーは身悶えた。ヴェインはエドガーの性器を握っていた右手を左手に変え、先端からびゅくびゅくと溢れる液を右手の人差指ですくい取り、ゆっくりと尻の谷間に塗り込めた。ちょうどその真中あたりの窄まってる箇所が指をつぷん、と飲み込んだ。
「……っふ、あ……」
エドガーが身体を震わせる。まるで金色の糸のような髪の間から見え隠れする苦悶の表情に、ヴェインは息を飲む。そのまま中指も差し入れる。2本の指を根元まで飲み込ませると、エドガーはシーツを握りしめ、身体をぶるぶると震わせている。もう片方の手で握りしめた陰茎の先から半透明の液がポタポタと滴り落ち、シーツを濡らす。
「たまらないよ、エドガー。」
そのまま指をくちゅくちゅと動かすと、その動きに合わせて腰が淫らに跳ねる。
「一晩中、こうやって君を苛みたい。」
「…私…は、とても、…耐えられそうに…ない…な…」
息も絶え絶えなエドガーに、ヴェインは嬉々として尋ねる。
「苦しいか?」
「とてもね。」
顔は笑みを作っているものの、エドガーの目元は朱に染まり、流した涙で目元はぐしょぐしょだ。ヴェインはその笑みに笑顔を返すと、なんの前触れもなく、薬指をエドガーの蕾に強引にねじ込んだ。
「…、は、あ、あ、あ!」
エドガーが背を反らせ、身体を痙攣させた。痛みと快感がないまぜになり、射精を促すのだが、根本をきつく縛られせき止められたそれは下腹にずん、と重く響き、エドガーを苦しめる。
「私を愛しているというなら、懇願してくれないか、エドガー。」
「…そう、やって…ねだられる…のは、悪い気は…しない…な。」
「違うな。」
ぐちゅ、っと大きな音をさせ、ヴェインは腹の裏側の辺りをえぐる。その刺激にエドガーはシーツを握りしめて身体を大きく硬直させ、崩れ落ちた。
「ねだっているのは、君だ。」
エドガーはベッドに身体を沈め、全身に汗をかき、肩で大きく息をする。
「……君は、本当に……素直じゃ、ない…な、ヴェイン…」
「互様さ。」
苦しい息の下で、それでもエドガーは肩越しにヴェインを見、笑ってみせる。
「…もう、とても耐えられないよ、ヴェイン。」
「もっとだ。」
「君が、欲しいんだ。」
「なんとも甘美な言葉だな。」
ヴェインはエドガーの蕾に自らの先端をあてると、ぐっと腰ごと押し付けた。
「!!…っくぅっ、ッ、う、はぁ………っ!!」
エドガーの背がまたもやぴん、と強張る。熱くて怒張したそれの先端が入り口をくぐり抜け、ずぶずぶと中へ、中へと埋められていく。内臓から喉元まで迫るような圧迫感に、エドガーは陸にあげられた魚のように身体を跳ねさせ、口は酸素を求めて開閉する。
その全てを受け入れると、苦痛は徐々に和らぎ、変わって脳みそが溶けそうな快感が繋がった所から沸き上がる。が、一方でそれは射精止められ、出口を失った欲望をも刺激する。とろけそうな快感とせき止められた射精感にエドガーは意識が飛んでしまいそうになる。
「う…わ、…あ、ヴェイン…!」
そんな状態でヴェインが激しく腰を動かし始めたのだ。無意識に逃げようとするエドガーの腰を捕らえ、奥へ、もっと奥へと突き立ててくる。快楽に溺れたいのに、きつく根本を縛られた陰茎は苦痛をうったえ、エドガーはもうまともな思考がはたらかない。
「…も、…解…いて…くれ…っ…」
エドガーの哀願に、ヴェインも繋がったそこにどくん、と更に血液が集まった気がする。
「…ぁ、アッ!ヴェ…イン……っ!」
一気に加速した抽送に、エドガーは身体ごと揺すぶられる。ベッドがギシギシと大きく軋む。
「エド…ガー……っ…」
ヴェインの掠れた声が聞こえた。自分の胎内で、それが限界まで膨らんでいるのにエドガーも気付いていた。ぐっと最奥が突かれる。ヴェインの固く反り返った性器がエドガーのもっとも感じる箇所を裏側からゴリゴリと抉る。まるで白い刃が脳を切り刻むような快感で。さすがのエドガーももうこらえ切れず、イカせてくれ、と苦しい息の下でうったえかけると、ようやく根本を縛っていた布切れを解かれた。陰茎の中の道を、ものすごい勢いで快感がせり上がり、はじけた。どろどろとした液は勢いよく押し出され、シーツにぱたぱたと落ちていった。同時に胎内でヴェインが射精したのを感じ、エドガーはぐったりとベッドに崩れ落ちた。
********
さっきまで身体を重ねていた相手が部屋を出る気配を、エドガーは夢うつつで感じていた。やはり、男同士のセックスは身体に負担をかけるようだ。指一本動かせない。
「…だが、快感は…女性とは比べ物にならない…な…」
エドガーは大きく息を吐いてた。さっきまで重ねられていた、あの体温が恋しい。
(だが、これは恋ではない。)
共鳴だ、音と音が響きあい、空に散って消えてしまう。だが、その刹那の美しさにエドガーはヴェインを見る。
「愛しているよ、ヴェイン。」
そのあとに”可哀そうなヴェイン”と続けて、エドガーは目を閉じた。
おわり。