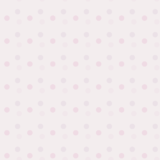この記事を読むのに必要な時間は約 10 分です。
ガブドレですが、中途半端で止まっていて、しかもガブラスは一瞬しか出てきません。
ドレイスは記念式典があまり好きではない。
お祝い的な要素が強くなると、ジャッジの鎧ではなく、式典用の礼服を着なくてはならないからだ。どういう理由か、女性用のジャッジの礼服はスタンドネックの軍服風のコートジャケットに、ロングのタイトスカートなのだ。それでも軍服に準ずるものなので、いざという時に靴がスッポ抜けてはと、ブーツを履くのだが、そのブーツにしたって、5センチほどではあるが、ヒールもある。
プライベートではマニッシュなスタイルではあるが、女性用の服を着ている。当たり前のことだ。だが、同僚たちには自分が女性らしい格好をしているのが物珍しいのか、とりわけベルガなどは人を小馬鹿にしたようなことを言ってくる。
記念式典は喜ばしい行事ではあるが、自分が女性用の礼服を着た時の周囲の反応が、ドレイスを少し疲れさせていた。だが、ジャッジのひとりとして式典に出席しないなどと、とんでもない話だし、何よりも明日に迫ったその式典は、
(ラーサー様の……お誕生日だ……)
自分が命にかえても仕える主のめでたい席でこんな憂鬱な気持ちになるのはどうしたものか、とは思うのだが、ドレイスは小さくため息をついた。
そして、ふと思い出した。新しく着任したばかりのあの新しいジャッジマスターはどんな反応をするのだろうか?
*****************
ジャッジマスターが一人増える、という話は誰から聞いたのだろうか。
(そうだ……ラーサー様の警護につき、身を挺して守るように命じられたあの日だ…)
夕陽が帝都を染める。それを皇帝宮のバルコニーからぼんやりと眺めながら、ドレイスは思い出していた。
ジャッジとして帝国軍に名を連ね、ただひたすら職務に励み、数少ない女性のジャッジマスターとなった。その栄誉に預かったころの自分は、とにもかくにも、他のジャッジマスター達に恥じぬよう、女だからと言われぬよう、必死だったと思う。
(……それが、今ではどうだ……)
日々激務ではあるし、イヴァリースにはいつ破裂するかわからない火薬庫があちこちにある。帝都の中では飽きもしない権力闘争が続き、ある日誰かが突然居なくなり、そして今まで聞いたこともない者が宮殿に出入りする。そんな日々にドレイスは知らぬ間にすっかり馴染んでいた。導火線は自分の周りにたくさん転がっていて、そのどれにも火が点いている。そのことを正そうとしたり、糾弾しようとしたり、あるいは誰かを守ろうと意気込んだ日々もあったが、カーテンを開けるとまたそこにカーテンがあり、と、皇帝宮の中は、皇帝自身でさえもその最奥に辿りつけないのではないかと思う。
そんな風に危険で刺激に富んではいるものの、似たような日常が続く毎日に二つの印象的な出来事がドレイスに起こった。
一つ目は皇帝第三子のヴェインが長兄、次兄を謀反の疑いあり、で切ったこと。もう一つはグラミス皇帝自らラーサーを守るように命じられたことだ。そして、そのためにはもう一人、新しいジャッジマスターを任命し、共にその使命を全うせよ、との勅命を受けた。
「もう一人……ですか……」
「不安か?」
「いえ……」
大国の大帝のは彼の息子たちのことで悩んでいた。どれほどの権力を持ち、どれほどの重責を背負っていようが、
(やはり人の親か……)
「卿が女性ジャッジだから案じているのではない……」
「理解しております。」
ヴェインは聡く、抜け目がない。あれほどの知略を持つ男に一人で対抗するにはさすがにドレイスにも荷が重かった。と、いうことはもう一人のジャッジマスターは、
(ヴェインと張り合えるほどの者というのだろうか……?)
「仔細は追々知ることになるだろう。」
話はそこまでだった。
*****************
ラーサーに仕えることとなり、ヴェインが彼の兄2人を切った、という解釈がドレイスの中で変わっていった。兄2人を手にかけるという行為はたとえどんな大義があったとしても、骨肉相食む権力闘争の臭いがした。ヴェインが跡継ぎになりたいがための謀略なのか、それとも父の地位を脅かそうとしたのを防いだのかはわからない。だが、ドレイスには上の兄2人が謀反を企てるなど、とても考えられなかった。
しかし、そこに深い詮索をしようとはしなかった。グラミス皇帝が命じたのなら、それは間違いではないのだろう、と、それくらいの認識しかなかった。このような凄惨な話に鈍感になるほど、まるでそれ自体が禍々しい生き物のように、人を断罪し、陥れ合うこの宮廷の中での出来事がドレイスにとっての日常になっていたのだ。その中で自分らしさを保つこと、法に準じることがせめてもの矜持だった。
だが、新しい主を持ったから、その考えは日々変わっていった。
新しい主人であるラーサーはまだ幼く、愛らしかった。公式の場では挨拶の言葉を述べると、皇帝一家と敵対する元老院の細君たちが「んまぁー!」と黄色い声を上げるほどだ。ドレイスもお人形のような皇子だと思っていた。
だが、実際の彼は目をみはるほどの利発な少年で、聡明だった。しかもそれは兄であるヴェインの、まるでカミソリのように鋭い怜悧さとは違った。皇帝一族に名を連ねる者として、教わった帝王学を真摯に信じ、実践しているのだ。ドレイスが忘れていた清廉さがそこにはあった。
(この御方こそ……)
自分が仕えるに足る君主だと思った。ラーサーが全てを変えてくれるとは思ってはいない。ただ、その清廉さを守りたいと決意を新たにした。そんなとき、あの男がやって来たのだ。
グラミスですら詳細を伏せたというのに、耳の早い元老院の細君方がドレイスに教えてくれたのだ。話はそれるが、ドレイスはこの元老院の細君達が苦手だった。俗な世間話に日々興じ、香水と白粉の臭いを廷内に撒き散らす。害がない罪がないと見せかけておいて、時おりさそりのように毒の針をふるうこともある。
そんな彼女たちは、何故か自分に対してまるで舞台俳優のように麗しいだの凛々しいだのと歓声を上げるのだ。同僚たちにそれをからかわれ、いつの間にか有事の際の元老院の細君たちへのお膳立ては自分の役割になっていて閉口したものだ。だが、今では歓声を上げて自分に群がる細君達を喜ばせるような言葉を投げかけ、それなりの関係を築いてきた。最初はからかっていた同僚たちもドレイスの働きでぎくしゃくしていた皇帝サイドと、元老院側の関係がいくぶんか和らいだので、その裁量を認めざるをえなかったのだ。
彼女たちはドレイスを探していたのか、その姿を見つけたとたん、きゃあきゃあと少々けたたましい声を上げながらやってきて、あっという間にドレイスを取り囲んだ。
「ドレイス、あなたご存知?今度やってくる新しいジャッジマスター!」
さすが、奥方たちは耳が早い、とドレイスは苦笑いを浮かべるしかない。
「なんでも、元は下民だったそうよ?」
リーダー格が得意気にその情報を述べると、取り巻き達は口々に「んまぁー!」を連発し、栄えあるジャッジマスターに陛下は何をお考えだの、そのような卑しいものがわたくし達のドレイスと一緒に?だの、ラーサーさまにそのような者を近づけるなんて、などと勝手なことを、餌をねだる雀の雛のようにまくし立てている。
ドレイスはうんざりしながらも、誰があなた達のだ、とか、普段は皇帝一家を目の敵にしているくせに、などとドレイスは思ったが口には出さないでおいた。しかし、下民という言葉は耳に残った。
ドレイス自身は名家の出身ではあるが、出自で相手を見ないようにしているつもりだ。
(ましてや、それが有能な者ならば…だ…)
身分の低さにかかわらず、グラミスに見初められてジャッジマスターにまでなった男だ。
「それにね、聞いていて?ドレイス?その男はかつて帝国に反抗した、あのランディス共和国の出身だそうよ?」
それを聞いてドレイスの顔が引き締まった。
「そんな流浪の輩、ラーサー様に害があったらどうなさるのかしら?」
「ご夫人がた。」
ドレイスはニッコリと細君達に微笑みかける。頬を紅潮させ、瞳をうるませた皺だらけの白粉顔がいっせにこちらを見た。
「どうぞご心配なきよう。わたくしがこの目で、その男が信頼に足るかどうか確かめてやりますので。」
すると、細君たちはさすがですわ、ドレイスがいれば安心ですわ、ですわですわですわーっ!とさえずりながら、気が付くとどこかへ行ってしまっていた。
「……クソジジイめ……。」
誰も聞いていないのをいいことに、ドレイスは武人らしからぬ悪態をついた。
(ランディス出身だと…?)
自分が子どもの頃の戦乱で、と言っても帝都はまったくの無傷で、まだ幼かったドレイスはその戦勝の祝賀会に出たことを覚えている。確か、皇帝宮に行儀見習で入った頃だ。その敗戦国から敵国のジャッジマスターになった男をラーサーの警護につけるなど、
(陛下は…何をお考えだ…?)
その時、不意に背後から声がした。
「クソジジィとは誰のことだ?」
つづけたいです…